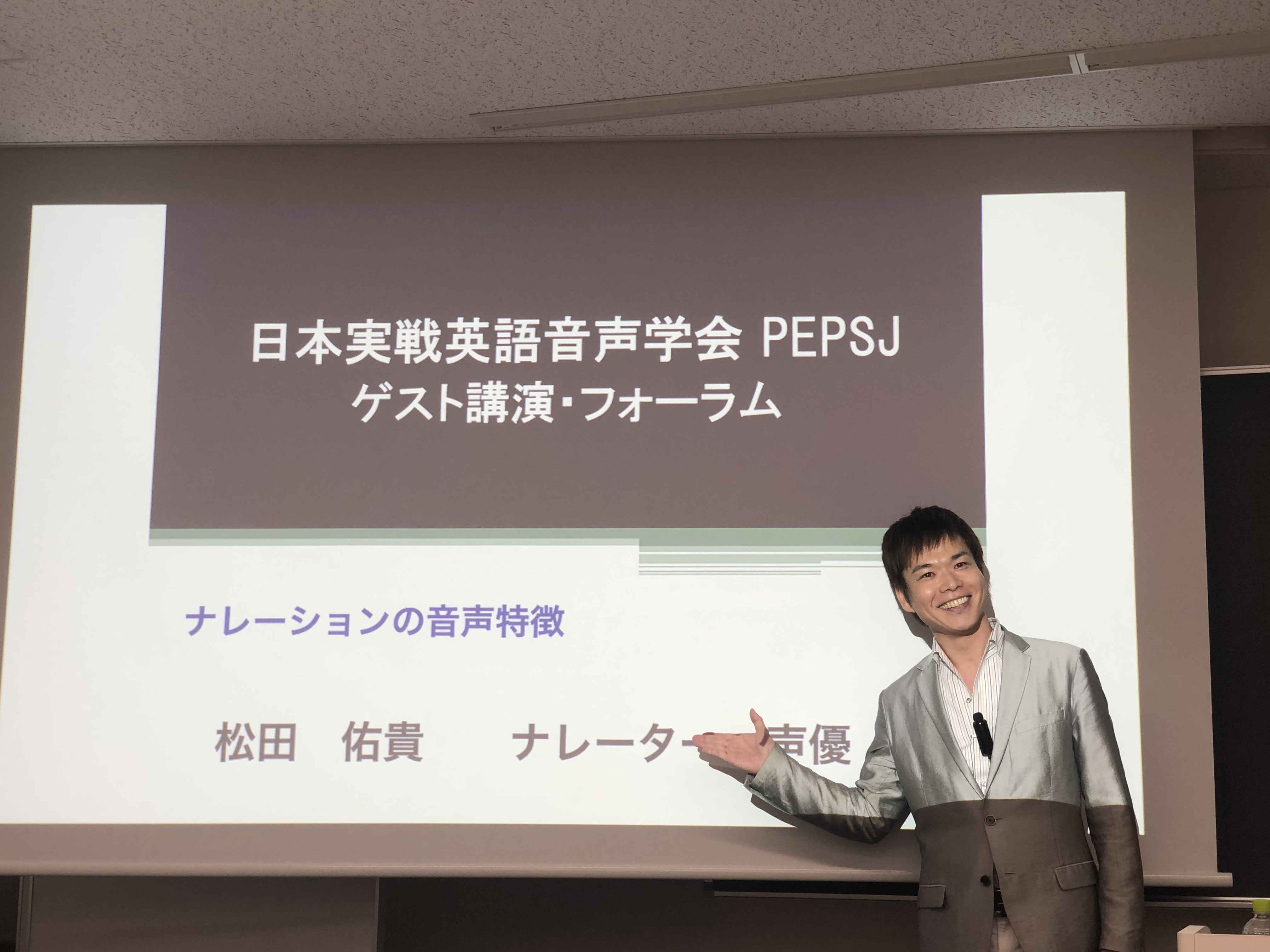水曜モードの復学Mです。
先日は武信さん、狩野さん、畠山さん、マネージャー陣によるスタジオ実習でした。
2種のバラエティー映像のナレーションをブースで録音し、その後批評、という流れ。
複数のマネージャー側の「売る視点」からの意見は、実際の市場で勝ち残っていくには?のヒントが盛り込まれた、リアルなものでした。
私は、今、自分が強化したい部分(今後強みになるかもしれない部分)の表現でチャレンジをしたのですが、頂いた原稿には合わないプレイに… 「在学中だから、強化分野にチャレンジすることはOKだけど…この原稿はあなたの場合○○な感じで読んだ方が合うと思う」
「別の場所で指摘されたこと(今回の私の場合はボイスサンプルで強みを絞ること)を、次の現場に持ってっちゃだめだよ、原稿によって違うんだから」 現場では臨機応変に原稿に合ったプレイにしないと…
頂いた原稿が生かせないプレイでは何の意味もない。自分よがりのプレイになっていたことに気づきました。
実戦の時、原稿とどう向き合うのか、原稿をどう理解するのか、が大切であること。
(自分の強み(にできるかもしれない部分)を鍛えることと、その時々で頂いた原稿を一番ベストな形で表現することは別。)
そして、その原稿・VTRを輝かせるために、自分という楽器を用いて、どうプレイすればベストなのか、その時、その時にしっかりと判断できる理解力とセンス…鍛えていきたいです。