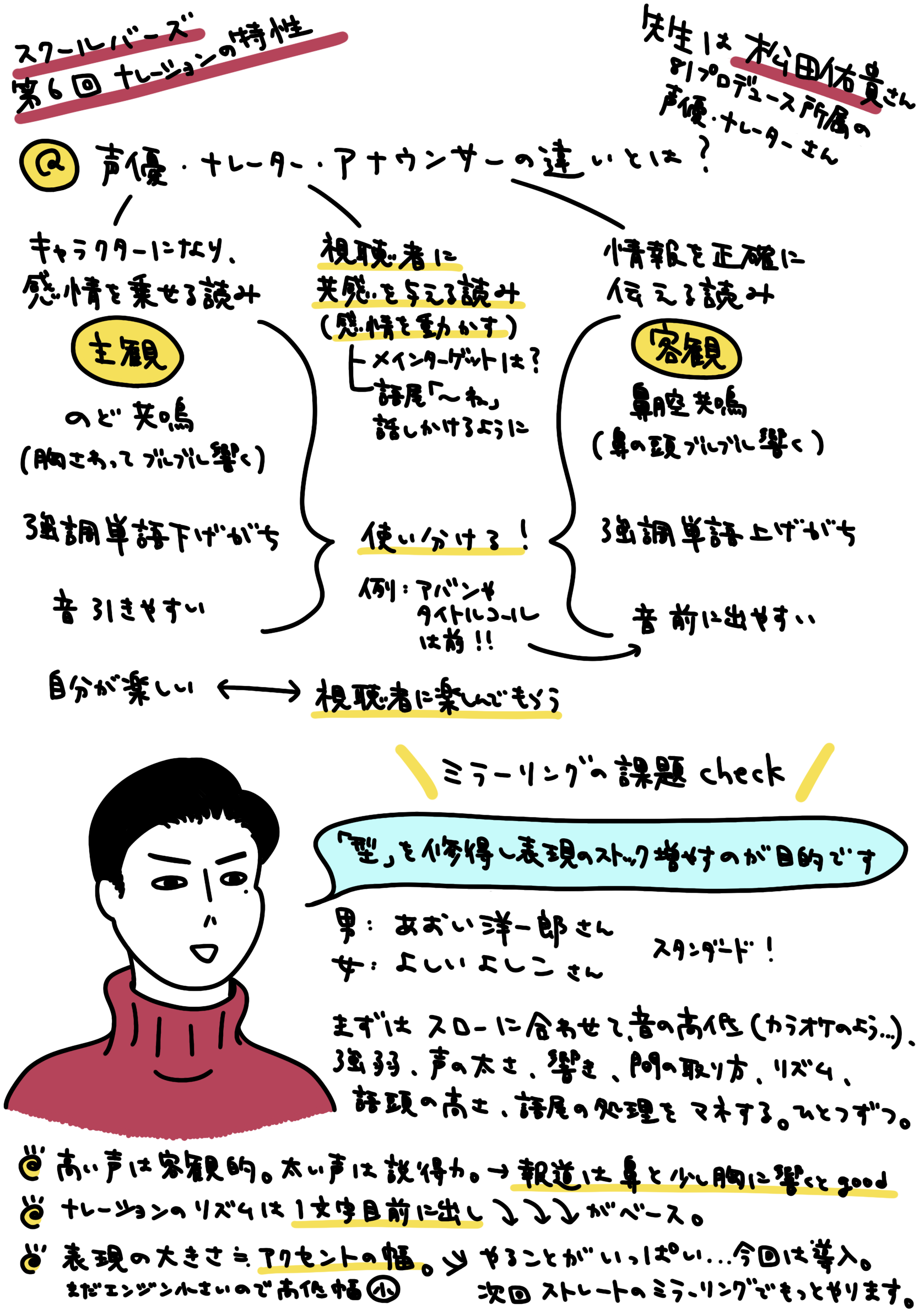皆さんこんにちは。575以外のブログタイトルの「型」を思案中の、秋17期モードの北村です。
「私たちはライターじゃないんだから、ブログ書くときにうまくアウトプットしようなんて考えなくていいんだよ。それよりも、ちゃんと言葉として残しておくのが大事」と、コアのときのアフターバーズで墨屋先生にご助言をいただいたのですが、バーズの内外を問わずいろいろな方がこのブログを見ていると思うと、何か自分なりの工夫をしたいななんて考えてしまうものです。
さて、前置きが長くなりましたが、先日は狭川さんの「VO役幅のレッスン」でした。VO初挑戦ということで、久しぶりに座学→実践の流れでした。
座学の主な点は、
・VOは一人でたくさんのキャラクターを演じなければならない。
・「次もこの人呼んでみたい」というインパクトを与えるのが大事。
・音の緩急や高低、年齢設定などでパターンを増やす
・声優のように魂ごりごりはほぼNG
・逆に魂入れて面白くして良いときもある
ということで、いざ実戦へ。
やってみると、これまた難しい。ナレーションのとき同様、「悪くはないけど、可もなく不可もなくだからもう少しインパクトがほしい」とのことでした。
少し経ってから授業の録音を聞いたのですが、まあ単純にすべてが引き出し不足だったようです。前の大江戸さんの授業の際は、「ボイスオーバーいいですねえ」なんていうお褒めの言葉をいただいたので「なんでだろう?」とは思ったものの、よくよく考えてみるとあの時のボイスオーバーは犬だったので何でもありだったからだなあと。
ボイスオーバーは実在する人間に声を充てることがほとんどだと思うので、人間に充てるボイスオーバーも研究していきたいと思います。
余談ですが、その日の授業は「なんか新鮮」と思っていたのですが、よくよく考えたらクラスメイトがセリフをちゃんと読んでいるところを初めて聞いたからかもしれないという結論に至りました。
普段はナレーションを扱っているので、あまり聞けない声が聞けて面白かったです。
ということで、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
本日も笑顔120%な1日を。